|
�͂��߂�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
|
|
�F�l�œ����ݏZ��Us����Ɉē����Ă��炦��Ƃ������ƂŁA7�����O�A�x�𗘗p����Hr����ƒ���ɏo�������B �\���15�A16���̓V�C�\��͉J�m��70���A�ǂ����悤���Ɩ��������A���́u����j�v���Ƃ��Ȃ�ł��傤�A�Ɨ\��ʂ茈�s���邱�Ƃɂ����B 14������5���o���B �r����{�߂��Ŏ��̎Ԃɂ��a��������������ł��ߌ�2���ɂ͐z�K��IC�ɓ��������B �������ɓ��}�R�Ɍ��������B �ӂ��Ƃł��W��1000m�A�ǂ�ǂ�o��B�刢�������A�������邩������Ȃ��ƃJ��������ɒT���J�n����B �V�����̏b���ɃL�}�_���q�J�Q�ɍ������Ă�������W�܂��Ă���B �b���o�b�N�̎ʐ^�ł͂ƒǂ��������̏�ɗ��܂点�悤�Ƃ��邪�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂȂ�Ȃ��B ����ł��Ȃ�Ƃ������B�e�����B ���炭�������T���������Ԃ����Ȃ����ɂ߂ڂ����`���E�̋C�z�������̂ň�U�`�F�b�N�C�������ꂩ��ɂ��悤�ƌ����̃y���V�����Ɍ��������B 4�������B 6���ɒT���I�����A�߂��̉���ɓ���A7���[�H�A�r�[���Ŋ��t�����B �����ɂ̓e���r���Ȃ������ɖ��C�����ċ㎞�O�ɂ͂��łɖ��̒��B 1���ڂ��I�������B �O���݂�ƐI���̓V�C�\��͂����������������A��͂�u����j���v 8���ɐz�K��IC�ŋ�������ƍ����A�唒��ѓ��Ɍ������B 10���O�ɓ����B�Ԃ��~�߂ċ߂���T������Ƒ����̃Z�Z�����Z������щ���Ă���B ���̒��̏����傫�ȃL�o�l�Z�Z�����B�e����B ���炭�i�ނƐ����̃[�t�B���X���ڂ̑O�̏����`���`����щ���Ă���B �E���L���V�W�~�A�����ŃW���E�U���~�h���V�W�~���t��Œ�܂��Ă���̂������B�e����B �͐�H���̋x�e��������A��ƈ��̕��Ɂu�ŋ߂ǂ��ł����v�ƕ����Ɓu�J�オ��̎��Ȃǂ��̂�����I�I�C�`�����W���ǂ��o���v�Ƃ̕Ԏ��A��R���C�t���A�X�ɗѓ���i�ނ��A�Z�Z���A�L�}�_���q�J�Q����B �A�T�}�V�W�~�̃|�C���g�ł͂قƂ�ǃq���V�W�~�A�ł��I�X�̗ڗ��F�A���X�̓��F�͂��������Y��ŁA�ʐ^�Ɏ��߂�B ���̍H������Ɉ����Ԃ��ƁA�G���^�e�n�ɃV�[�^�e�n�A�����ăN�W���N�`���E�ɃX�W�{�\���}�L�`���E�A��Z���E�������ł���B ���������ړ��Ắu�I�I�C�`�v�͂��Ɍ���Ȃ������B���ɍ��{�b�`�R�Ɍ������B �w�O�̃r�W�l�X�z�e���փ`�F�b�N�C�����A���C�ł����ς肵����߂��̈��݉��Ŋ��t�����B �����͒���n���͑�J�����ӕo�Ă��薳�������Ǝv���A�s���v����������10�����A�Q�����B �u�R���̕��͂܂��Ȃ悤�ł�������n�����ߌ�͏����ǂ��Ȃ�ł��傤����v�ƁA7���ɂ̓`�F�b�N�A�E�g�B �߂��̃R���r�j�Œ����H���d����A�z�K�̂قƂ�Œ��H�����܂����̂��A�R�����B��̃~���}�V�W�~�|�C���g�Ɍ��������B �r���~�������肾�������|�C���g�ł́A���x�~�B �T�J�n�`�`���E�A�z�V�~�X�W�A�~�X�W�`���E�ȂǕ��ʎ�͂��邪�A�c�}�W���͌���Ȃ������B�J�����~��Ȃ������������Ƃ�Ȃ��Ƃ��߂炵���B �����I�ɂ�����������������Ȃ��B���т��ς܂��āA�Ăѐz�K���ʂɈ����Ԃ��A���P����������B �J�͏オ���Ă��邪�A��̕��͖����������߁A�܂�œV�ɏ���悤���B �r���ӂ�T���A���ނ��~�������Ă����ƁA��������q���E�����`���E����R��яo���B ���������ɏꏊ��ς����Ƃ���ŁA�A�T�}�V�W�~�A�����ăV�[�^�e�n�X�ɐi�ނƃM���{�V�q���E�������A�U�~�ŋz�����Ă���̂ɏo��B 5���߂��Ȃ�A���܂�x���Ȃ�߂��Ă��Ƃ����őS�������I�������B 5���Ɍ��n�o���A�z�KIC���獂���ɓ���B�A��͐��ʂɘb���͂��ށB �r���[�H�x�e�A�g�C���x�e���Ȃ���⍑�ɂ͖钆�̈ꎞ���ɖ������������B �S���s������1800km�ł������B �M�B���I�s�i2007�N�j�|����z�K�`������`���R�s�|
����́A�V����Om�������AHr������AUs����Ƃ�4���ł���B �I�I�S�}�V�W�~�A�c�}�W���E���W���m���Ȃǂ���ړI�ł���A����ɍ��킹��8��4���A�⍑�𑁒����O��Om����̉^�]�ŏo�������B ��N���l�A�܂����}�R��ڎw���A�ߌ�3�����ɂ͓��}�����ɒ������B �����ŃG���^�e�n�ȂǍ�N�Ƃقړ�����̎ʐ^���B������A�k�m�s������̃������A�J�V�W�~�|�C���g�Ɍ��������B ���ɂ��Ȃ�x���������A�N���A�I�j�O���~�̖Ȃǂ���@���ƃ������A�J�V�W�~��I�i�K�V�W�~����яo���A���̓��A�������A�J�V�W�~�̌���̂Ȃǂ�������A�B�e�ł����B ���}�n���m�L��@���Ɛ����̃~�h���V�W�~����яo���A�B�e�ł����B 7���O�ɂ́A�h�ɋA��A��}���Œ��H���ς܂��A�ēx���}�R�Ɍ��������B �R�����̖q����ѓ���i�ނƁA���X�ƒ�������A�ړI�̃c�}�W���E���W���m�����ꓪ������ʐ^�ɂ����߂邱�Ƃ��ł����B �ꎞ�ԋ߂��i�����肪�A���̃|�C���g�ŁA���l�̍̏W�҂������̂ŗl�q���Ȃ��炻�̎��ӂ�T�������B ���X����邪�Ȃ��Ȃ��Ƃ܂��Ă��ꂸ�A�ǂ��ʐ^�͎B��Ȃ��������A�؋��ʐ^���x�͎̂B�邱�Ƃ��ł����B ���̎��ӂł́A���̑��t�W�~�h���V�W�~�A�I�I�~�h���V�W�~�A�E���L���V�W�~�Ȃǂ̃[�t�B���X�����邱�Ƃ��ł����B �ߌ�O���߂��ɑS�������I�����A�r�ɕt���B �⍑�ɂ͖钆�̈ꎞ�߂��ɖ������������B
�Δn�����I�i2008�N�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���s����Gt����́A�Δn�ɂ͉ߋ�������s���Ă����邪�A�ʐ^���B�蒼���ɍs�����Ƃ����̂ł������邱�ƂɂȂ����B �Ώێ�ɍ��킹�āA�o����5��26���A�V�����A�n���S�A��s�@�����p���Œ��O�ɂ͑Δn�ɓ��������B ���X�g�������̃G�m�L�̎�����S�}�_���`���E����щ���Ă���B �܂��{���̃c�V�}�E���{�V�V�W�~�̑����Ƃ����k�Ɍ������AGt���ߋ��ɂ悭�����Ƃ����㌧�����{�ގ��ӂ�T�����邱�Ƃɂ����B ���ӏ����̃|�C���g�ɓ��������A�c�V�}�E���{�V�ǂ��납�قƂ�ǒ����ڂɕt���Ȃ��B �A�I�X�W�A�Q�n�A�R�~�X�W�A�����V���`���E�Ƃ��������ʎ킪���܂Ɍ������x�A����ł��Δn�Y������ƎB�e�����B�����������Ă�����A����������ѓ������Ń~�X�W�`���E���ڂɎ~�܂����B �Δn�Y�͏��Ԃ�Ŕ��т��L���Ȃ����������b���B�e�ɐ�O�������A�ړI�Ƃ����c�V�}�E���{�V�͈���������Ȃ������B ����ł̓g���{���A�Ɩڂ��Â炷���A���ȏ�ɂ��Ȃ��B�c�V�}�E���{�V�́A�����I�ɂ܂��o�Ă��Ȃ��̂��A����Ƃ��������������̂��B �����������������߁A��̐������Ȃ��A�S�̂Ɋ����C���ł��邵���҂ł��Ȃ������Ƃ���ߊϓI�ɂȂ�B �����́A���܂萬�ʖ����h�ɂɌ��������B�@ �ό������Ă������ƁA��Δn���̊؍��W�]���֗������L�O�B�e������A�O���̃|�C���g�߂��������B ��ɓ����Ă݂���������l���̎p�͌������A�|�C���g��ς��悤���Ƙb���Ă����Ƃ���A�u�����}�I�v��Gt����A�e�̑��n�ɓ����čs�����B ���[���炻������Ă����Ƃ��돬�������̂��`���`�����Ă���̂��ڂɓ������B �u�����A���}�g��������܂��A�`���`�����Ă��܂���d�v�����Ɋm�F�Ɍ�������Gt����u�E���{�V�ɊԈႢ����܂���v�B �Ƃ���Ɍ��C���o�Ď������n�ɓːi�B Gt����̎w������������ƁA���߂Č���c�V�}�E���{�V�V�W�~�̉��Ȏp�B �u���ꂪ�c�V�}�E���{�V���A���킢���Ȃ��v�u����ĂȂ��Ă������܂���v�Ƃ̐������ɋ����C���ɃV���b�^�[������B �����ł�3���m�F�������A������������Ǝv���A����ł͂ƁA����̃|�C���g�Ɍ��������Ƃ���\�z�ʂ茻��Ă���A���낢��ȃ|�[�Y�̎ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B �ߌ�́A��Ɍ������A�����A�L�Ƃ���炵���|�C���g�ɗ���������Ƃ��낢����̃|�C���g�ł����������邱�Ƃ��ł����B �L�ł́A���������̉Ԃɑ�R�̃A�Q�n�`���E����щ���Ă���A�������ɑΔn�Ǝv�킹�����A���R�ɂ��^�C�����V�I���g���{���B�e�o�����B�Z�����\��ʂ�z�e���ɓ����A�O���Ƃ͈�����r�[���𖡂키���Ƃ��ł����B ����ł͒����ɂȂ�Ȃ��B���x�͂������邩������Ȃ����A�\�肵�Ă����ꏊ�����ł����Ă������ƁA�����������@�����w������A�����|�C���g�����č�Ɍ��������B ���č�ɓ����������́A�J������܂�A�����͒T���o�������A���̓��܂��J�����������Ȃ����̂ŋ�`�Ɍ��������B �\��̕ւ͌��q�ł����ꔑ���邱�ƂɂȂ������A���̉����Ŋm�F��������29��A�g���{��5��ŁA�����̂��Ƃ��l����Ζ������Δn�����ł������B
6��23������Gt����Ɖ��������ɏo�������B ���������Ƃ����A���Y��̃A�J�{�V�S�}�_�����L���ł��邪�A���i�Ǖ��̃R�m�n�`���E�ق�����n�̒������낢����҂ł���B ������`9��30�����A��������`�ŏ�芷���A���V����`�ɂ�12���ɓ��������B �����Ƀ����^�J�[�Ō���83�����Ɍ��������B �V�钬�����ؖ��ŁA�e���ɓ����Ă݂��Ƃ���A���ɂ͏��߂ẴA�I�^�e�n���h�L��q���V���r�A�V�W�~���V��ł���A�X�ɏ��̏�������A�J�{�V�S�}�_�����ڂɓ������B �A�J�{�V�S�}�_���́A�������ߖ]���ł̎ʐ^�����B��Ȃ��������A�����Ȃ�̖{���o���łȂ��Ȃ��̍K��̗ǂ��ł���B ���炭���ӂ�������Ƃ���A�^�C�����N���{�V�V�W�~�A�����E�L���E�~�X�W�Ȃǂ�����A�B�e�ł����B�������X�ɓ쉺���A5���O�ɂ͈ɐ咬�ɓ������B �����́A120�܂Ő����A�������E��ɔF�肳�ꂽ��d���̐��a�n�ł���A�悸���̋L�O��i�����j��K�ꂽ�B �@�@�@  ���̓����̂�����ӂ����̃|�C���g�ƂȂ��Ă���A���炭�T�����������ɒx���������Ƃ�����A�����E�L���E�q���W���m���Ǝ��������A�J�{�V�S�}�_�����ڂɓ��������炢�ł������̂ŁA�����͂���ŏI�����A���V�����̃z�e���Ƀ`�F�b�N�C�������B �c�}�x�j�`���E�A�A�}�~�E���i�~�V�W�~�A�����E�L���E�A�T�M�}�_���A�V���I�r�A�Q�n�A�E�X�C���R�m�}�`���E�Ȃǂ̓���킪���X�ƌ��ꂽ�B ���̓��A�A�J�{�V�S�}�_�����Ⴂ�Ƃ������ł���̂������ǂ������čs�����Ƃ���A���Ԃɓ����čs���A��u�����������A���̕ӂ�T���A������Ă���̂������B�e�����B �����哇��`����́A�����^�J�[�Ō���82����쉺�A�������Ԕ��̘e���ɓ������Ƃ���ŁA�V���Ƀx�j�����A�Q�n�����邱�Ƃ��ł����B ���炭�T���̌�A�����s�̒��S�X�����̎R�r���ɂ���z�e���ɓ�����2���ڂ��I�������B �����ł͕��ʎ�₱��܂łɌ��������ɍ������āA�V���Ƀi�~�G�V���`���E���B�e�ł����B10���߂��ɁA����ƃA�J�{�V�S�}�_��������A�Y���V�[�����B�e�ł����̂ŁA���̖ړI�n�Z�p���Ɍ��������B 11���߂��ɐ����Ԃɓ����A�͐�̏Z�p�여����Ƃ���ǂ���T�����Ȃ���k�サ�����A�A�}�~���������g���{�Ƃ������ꂢ�ȃC�g�g���{���������x�ŁA���ɐV����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B �����œ��p�x�Ɍ����������A�V���~�C���Ƃ������Ƃ������Ă��A�����ł����̎p�͏��Ȃ��A�����ŒT���͏I�����A�R�r���̃z�e���ɋA�����B ��30���œ����������A��`�ɒ����Ƒ�J�������̂ŁA��U�A�a�����̏h�Ƀ`�F�b�N�C�������B �ߌ�4������ɂȂ�A�J���~�̂ŁA�����x���������A���̐����m�����ɂ���ō��n�_��R�i240���j�ɍs���Ă݂��B �ō��n�_�ɒ����Ȃ�A���������̖k���Ƃ��ėL���ȃR�m�n�`���E�����ꂽ�B ���X���ꂪ�{��̖k���ł��������A1980�N��ɂ����Ŕ�������蒅�����Ƃ��ꂽ��ŁA�l�דI�Ȉړ��̉\��������Ƃ������킭���̒��ł���B �O���̃|�C���g��R�̂ӂ��Ƃ̐l�Ƌ߂��̉ԏ�ł͉���ނ��̓���n�̒����������Ă���A����܂łɌ��������ł��������A�����̎ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B �܂��A�R���ɋ߂��Ƃ���ł́A�����̃R�m�n�`���E�����邱�Ƃ��ł����B �ߑO�ő�R�ł̒T���͏I���A���ɁA����2�Ԗڂɍ����z�R�Ɍ��������B ������]�ɂł���W�]����������������Ă���A�����ɂ͊��L�Ə��N�ƎR�r�Ƃ����s�v�c�ȑg�ݍ��킹�̃��j�������g������K���l�������悤���B �����������炭�U����A���i�Ǖ���`17��20�����A��������`�A������`�o�R�A�V���������p���A�⍑�ɂ���10���߂��ɓ��������B �����ɂ��ẮA�������ŁA����ނ��͌��Ă������A����������ł͎������߂Ă̎B�e���s�ł���A���߂Č����������A�L���Ɏc�鉓���ł������B
�k�C�������I�i2009�N�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 7��6������F���s��Gt����Ƒ��R�[���������v��ŎB�e���s�ɍs���Ă����B �k�C���́A�ό��ł͍s�������Ƃ����邪�A����ړI�ɍs���̂͏��߂Ăł���B ���̎����́A�t�ƉĂ̒��̒[�����ɂȂ�Ƃ������Ƃł��邪�A�I�I�C�`�����W�ɂ͒��x�ǂ������ł���A�܂��ꏊ��ς�����Ȃ�ɑ����̎킪������̂ŏ��߂Ă̎��ɂƂ��Ă͗ǂ��ł��傤�Ƃ���Gt����̍l������ł���B �����`�ɂ́A�R���A�L������͒��s�ւ��Ȃ����߉H�c�o�R�ōs�����Ƃɂ����B ����ɂ͌ߌ�3���O�ɓ����A�����^�J�[����A�����ɍŏ��̗\��n�x�ǖ�Ɍ��������B �x�ǖ�Ƃ������x���_�[�A���x������̎����ł������������͑f�ʂ肵�Čߌ���O�ɕz��ʐ쉈���̗ѓ��ɓ��������B ���Ȃ�x�����Ԃł͂��������ѓ�������t�߂ł͑�����F�N�₩�ȃN�W���N�`���E���o�}���Ă���A�߂��̒n�ʂł́A�G�]�X�W�O���V���`���E�A�V�[�^�e�n�Ȃǂ��V��ł���B �����ł́A��������U��̃G�]�V���`���E���x��ł����B �y���݂𖾓��Ɏc���čŏ��̏h�ɂɌ��������B �`���o�l�Z�Z���ɍ������ăR�L�}�_���Z�Z���A�X�ɊD�F�̑�U��̃V�W�~�ł���J�o�C���V�W�~�A���Ŗ{�y�̂��̂ɔ�ׂ�Ǝւ̖ڂ͏������S�̂ɔ����ۂ���u�ʎ�̂悤�Ɍ�����q���E���i�~�W���m�������ꂽ�B �ЂƂ�����B�e���������̃|�C���g�Ɍ������B �I�I�C�`�����W�͂Ȃ��Ȃ�����Ă���Ȃ�������12�����ɂȂ��Ă���Ɠ���Ɍ��ꍂ�����ɗ��܂����B ����ł͂قƂ�nj������A300�~���]���ł���Ɗm�F�ł���B�؋��ʐ^�ɂ͂Ȃ�ł��傤�Ɖ������B�e�����B �L�x���^�e�n�����ꂽ������͗ǂ��Ƃ���ɗ��܂��Ă��ꂸ�B�e�ł��Ȃ������B ���낻��ꏊ��ς��悤�ƈړ�����r���A�ԑO���Ƀ~�X�W�`���E���������̂ŎԂ��~�߃J�������������B ����ƃt�@�C���_�[�ɕʂ̌̂��o�Ă����B�u�����ЂƂ�������݂����ł��ˁv�u���ꂪ�I�I�C�`�ł���I�������B���Ă��������v�Ƃ�Gt����̐������ɂ͂��C������}���Ȃ��炻��肻���Ƌߊ��V���b�^�[������B �\�}�͍��ЂƂł��������A��قǂ̉��ڂ̎ʐ^�ɔ�ׂ�܂��܂��̎ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B �C�`�����W�`���E�Ƀg���t�V�W�~�A�{�y�̂��̂Ƃ��܂�ς��Ȃ��l�����B�e���Ă���Ƃ����ɃR�~�X�W�����ꂽ�B ������͖{�y�̂��̂ɔ�ׂ�Ɣ��̕������ُ�ɕ��L���ʎ�̂悤�ɂ�������B �����Č��ꂽ�̂��J���X�V�W�~�A���܂��Ă����̂͂ق�̈�u�ł����������Ƃ��V���b�^�[��邱�Ƃ��ł����B �q���E�X�o�V���`���E������Ȃ��ɔ��ł���̂��A���ɂ����܂肻����������ɗ��܂�Ȃ��B �ǂ������܂킵�Ă���Ɖ�������u������ɃI�I�����V���`���E�����܂���B�q���V�W�~���I�v��Gt����̐��B �}���ŋ삯�����̉��Ŕ��ł���I�I�����V����ǂ��������܂�̂�҂��ĎB�e�A�����Ńq���V�W�~���V���c���N�T�ɗ��܂����Ƃ�����B�e�����B���ǃq���E�X�o�͎B�ꂸ���܂��łQ���ڂ��I�����B ���x��������}���Ă���A���̂��イ�����~���l�߂��悤�ȉԔ��͂Ȃ��Ȃ����������̂�����̂ł������B �J�͂��ł����̊����ł͒����o�Ȃ��͕̂������Ă��邪�A�ꉞ�\��̃|�C���g�ւ͍s���Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�����R�n���������B �\�肵�Ă�����I�C�쉈���̗ѓ������������ɒ������ɂ͉J�͏オ���Ă������������̊����ŗ\�z�ʂ蒱�̎p�͂قƂ�nj����Ȃ��B ���ł��̓��̏h���n�ł���эL�Ɍ��������B �r���A��I�C��̉͌��ŐQ���ׂ��Ă���L�^�L�c�l�̈�Ƃ��C������a�܂��Ă��ꂽ�B  ���������z���A�ߌ�4������эL�ɓ����B ���̍��͋C���������オ���Ă��Ă����̂ŗ����\�肵�Ă����쐼���̃|�C���g���������B �����ł̓E���W���m������щ���Ă��肻�̑��J�o�C���V�W�~�A�A�J�}�_���A�R�L�}�_���Z�Z���Ȃǂ��B�e���A6������\���쉷��̃z�e���ɗ����������B 8���Ƀz�e�����o�����k���̒����}�i�I�T���V�j�쉈���̗ѓ��Ɍ��������B �߂��ɂ����c�o���V�W�~���{�y�̂��̂ɔ�ׂ�Ɨ��̔���͏����߂ŕ\�̃u���[���ς���Ă��肵�炭�ǂ������ĎB�e�����B �ѓ���i�ނƕ��ʎ�ɍ������ăt�^�X�W�`���E�A�M���{�V�q���E�����A�R�q���E�����A�q���E�X�o�V���`���E�A�A�J�}�_���Ȃǂ����X�Əo�Ă����B �q���E�X�o�́A�����ł͉Ԃŋz�����Ă�����̂������ȒP�ɎB�e�ł����B �����ȍa�����ł͐F�̂��ꂢ�ȃC�g�g���{�i�ォ����ɒ������Ƃ����J���t�g�C�g�g���{�Ɣ����j�������B�e�����B �ߌ�́A�X�ɖk�̑��Ɍ������A��o�쉈���̗ѓ��Ȃǂ�T�������B���łɒx�����ԂƂ����Ă��N�W���N�`���E��G�]�V���`���E�Ȃǂ͂����������ł͖ڐV������͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �����4���ڂ̓������I����Z�����h���\��n�̍f������ɓ��������B ����ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂Ńz�e���ʼn���ɓ���Ȃǂ�����肵10�����ɏo���A�߂��̓���ᔎ���ق����w�����̖ړI�n�w�_���Ɍ��������B �r���T���\�肵�Ă����O�҂̃��s�i�X���炫�ւ�����߂��Œ��H���Ƃ�A�唟�A�����Ȃǂ֗������Ȃ���2�����ɂ͏h���\��n�ł���w�_���ɓ��������B �܂����Ԃ��������̂őw�_�����ό��A��������̊ό��q�ɍ������đ�Ȃǂ��B�e������A�������߂ł͂��������z�e���Ƀ`�F�b�N�C��������ł��낢���B ���R�k����́A�W��1000���A���R�̓o�R���̂ЂƂł���A�ڂ̑O�ɂ͐�k���L�����Ă����B ����������Ă݂����������ɒ��̋C�z�͑S���������X�ɂ�����ߋA�r�ɂ����B �����`�Œ��H�A1���߂��ɏo���A�H�c��`�A�L����`�o�R�Ŗ�10���O�ɂ͋A����B ���̉����͉J�Ɗ����ɂ����������\��̔������炢���������ł��Ȃ��������A����ł�41��̒����m�F���A���̓�35����B�e�����B�܂��J�̂������H�Ŋό����ł����̂ŏ\�������o���������ł������B �Ȃ��A����5����A10���̎��S�҂��o�������R�n�g�����E�V�R�ł������N�o�R�c�A�[����̃j���[�X�����ꂽ�B 6���A�����`�ɒ������Ƃ��͋C��30���x���z��������菋���������A����ł���A���ɉJ�ł��~��Ƌɓx�ɋC�����ቺ���A�{�x�Ƃ͑S���Ⴄ���Ƃ�̌����������ł��������B
�����Ƀ����^�J�[�Ŗk��A15�����ړI�n��X�����ɓ��������B ��`�ł͏��J�͗l���������A���̓��J���~�݁A��X�����̖��Ƃ̉ԏ�ɂ́A����̖ڗ��i�K�T�L�A�Q�n����V���I�r�A�Q�n���̑������̒�����щ���Ă���A�������ɉ���Ǝv�킹���B �`�g�쉈�������A�O��A�t�^�I�`���E�Ȃǂ������|�C���g�ɓ������T�����J�n����Ƃ����ɁA�����E�L���E�A�T�M�}�_���A�����E�L���E�~�X�W�A�����E�L���E�q���W���m���Ȃǂɍ�����A�C���J���V�W�~���ڂɓ������B �{��́A�ȑO�A���\���Ŕj�������̂��������x�ŐV�N�Ȍ̂�����̂͏��߂Ăł���A���̉��Ƃ������ʎᑐ�F�Ɋ��������B �[���܂ł��̏ꏊ�ŒT�����A���̂ق��A�}�~�E���i�~�V�W�~�A�^�C�����N���{�V�V�W�~�A�A�I�^�e�n���h�L�A�c�}�����T�L�}�_���A�E�X�C���R�m�}�`���E�A�i�~�G�V���`���E�Ȃǂ̓������B�e�����B �����A�O�邱�Ƃ̂ł����t�^�I�`���E�́A�����I�Ɉ��������̂����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B ���s����Kn����́A���̓g���{�ł���A���̎B�e������̖ړI�̈�ł��������A���̃|�C���g�߂��̐앣��r���ӂɂ͂��낢��ȃg���{�������A�ǂ���̂��A�ŁA�I�I�n���r���g���{�A�����E�L���E�M�������}�A�R�V�u�g�g���{�A�R�t�L�q���C�g�g���{�A�A�J�i�K�C�g�g���{�Ȃǂ��B�e�ł����B �^�ߐ쉈���̓y���_���̘e���ȂǂƂ���ǂ����蓹���Ȃ���A������w���K�ѕt�߂܂ŒT�������B �����ł́A���ɂƂ��Ă͏��߂ĂƂȂ郊���E�L���E�E���i�~�W���m�������邱�Ƃ��ł��A���̂ق�����܂łɌ�����ȊO�ł̓R�m�n�`���E�A�X�~�i�K�V�A�^�e�n���h�L�A���E���C�Z�Z���Ȃǂ̒��̂ق������E�L���E���������g���{�A�����E�L���E�n�O���g���{�Ȃǂ̓���n�̃g���{���B�e�����B �o�i�i�̊Q���ł���o�i�i�Z�Z���́A�[��ꎞ�ɂȂ��Ċ�������Ƃ������Ƃ��Ă����̂ŁA�����I�ɂ͂��邩�ǂ���������Ȃ��������A����Ă݂邱�Ƃɂ����B 18��������A�[�ł������Ă������A�o�i�i�̎�����щ�鍕���e���ڂɓ������B �o�i�i�Z�Z�����I����������悤���B ���̓��A1�����ڂ̑O�̃o�i�i�̗t���ɂƂ܂����B ���ɔ��Â��̂Ńt���b�V���B�e�����B Kn����́A�ߒ��Ԃ����o���ǂ��|���Ă������A�������̏W�����悤���B �����͎R�������X�ь����Ƃ��Đ�������Ă���A�W�]�䂩��͍��A�m���̒����݂���L����C�A�ÉF�����Ȃǂ�360�x��p�m���}�Ō��n����B �@�@�@�@  �R���܂ŎԂňړ����Ȃ���A�T���������A�����ł�����̖ڕW�̈�ł����������E�L���E�E���i�~�W���m�������邱�Ƃ��ł��A���̑������̓��������邱�Ƃ��ł����B �����ł������̒������邱�Ƃ��ł��������Ƀi�~�G�V���`���E�A�c�}�����T�L�}�_���������ڂɕt���A�c�}�����T�L�}�_���͌���ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B �ߑO�ō��A�m������ɂ��A�ߌォ�疼��s�������ɂ���^�쉮�_���A�`�g�A�^�߂ƈ�ʂ�܂��3���ڂ��I�������B �O��A���̎��ӂł̓R�m�n�`���E�𑽂����邱�Ƃ��ł���������͌�������Ȃ������B �V�����q���V���r�A�V�W�~���B�e���A���̂ق����ӂł̓R�V�u�g�g���{�A�I�L�i���`���E�g���{�Ȃǂ��B�e�ł����B ���̌��`�g�Ɋ�����Ƃ���ō���̒T���͏I�����A�쉺�����B�o���܂ŏ������Ԃ��������̂Ŏ�����w���A�ߔe��`15��30�����ŋA�r�ɕt�����B
�M�B���I�s�i2011�N�j�|�z�K�`������`���������|
8��2����11���O�ɐV�⍑�w�ŗ��������o���A�R�z���A���_�A���������ԓ��𑖂�A����7��������z�K��SA�ɓ��������B �����Œ��H���ς܂��A���z�K�����ʂɌ��������B �����ł��炭�B�e�������ƁA�k�m�s������̃������A�J�V�W�~�̃|�C���g�Ɍ��������B ���҂����������A�J�V�W�~�͂��Ȃ��������A�I�i�K�V�W�~�A�~���}�J���X�V�W�~�A�I�I�����T�L�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B �����ɂ͉ߋ��ɉ����Ă��邪�A���̎��Ɍ����E���W���m���A�M���{�V�q���E�����A�N�W���N�`���E�A�X�W�{�\���}�L�`���E�Ȃǂ̂ق��A�V�N�ȃc�}�W���E���W���m����A���̎����ł͗\�肵�Ă��Ȃ������L�x���^�e�n���P�����邱�Ƃ��ł����B �������̓��́A�V�C���v�킵���Ȃ������������A�N�W���N�`���E�������p�������������������̂ŁA���X�ɂ����͒��߁A�������A�J�V�W�~��������ƕ����Ă����z�K�s��a�Ɍ��������B �g�ѓd�b�ŁA���Hr����ɁA�|�C���g���Ȃ���T���Ă����Ƃ���A�P���̃������A�J�V�W�~�����ォ��~��Ă��āA�ڂ̑O�̃q���W�I���ŋz�����n�߂��̂Ŏ������p���Ȃ���B�e�����B �����ł͂��̑��I�I�~�X�W�A�~���}�J���X�V�W�~�A�I�i�K�V�W�~�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B �������A���쎩���ԓ����o�R���A8��30���A���n�����������̒��ԏ�ɓ��������B �@�@�@ ���t�g�̉��̕��ɂ͐F�Ƃ�ǂ�̉Ԃ��炢�Ă���A���܁A�x�j�q�J�Q�Ǝv���钱�e�������A���҂����������B ���t�g���~���ƁA�������炻�̉��̎Ζʂ�T�����Ȃ��牺���Ă������B�R�q���E�����A�S�}�V�W�~�A�q���V�W�~�Ȃǂ���яo���A�B�e�����B �S�}�V�W�~�́A�������ȂǂŌ��Ă��邪�A��������\���F�ł���̂ɑ��A�����̂́A�ʎ�Ǝv�킹��������A�����ɗ����b�オ�������B �����A�ڎw���x�j�q�J�Q�͎p�������Ȃ��B ��������߂ăQ�����f�������Ă��������A�J���~��o�����B �J������G�炵�Ă͂����Ȃ��̂ŁA�r�j�[���܂ŃJ�o�[���Ȃ���A�e���w�܂ʼn���A���炭�J�h��������B �قƂ�ǂ̓o�R�q�͂����ƃ��t�g�ɏ�艺���Ă������B ��X�����Β��߁A���̃��t�g�ō~��悤���Ƙb���Ă����Ƃ���A��⏬�~��ɂȂ����B Kn���A������ƍŌ�ɂ�����x���Ă��܂��Əo�čs�����B ���͊��҂��Ă��Ȃ��������A���炭����ƁA�P�����܂�����A�ƋA���Ă����B �\�����Ƃ���ɔ�яo���B ���x�J���オ��A�x�j�q�J�Q���A�N�K�C�\�E���V���c�P�Ȃǂ̉Ԃ̎�����������Ɣ��ł���̂��ڂɓ���A�����ǂ��Ă��炭�B�e�����B �V�C�\��́A���̓��́A�����ł���A��U�~��n�߂��J�́A�����~�܂Ȃ��Ǝv���Ă����̂Ŗ{���ɍK�^�ł������B Kn����̎��O�ɂ����ӂ����B 10������o���A18��30���߂��Ɋ⍑�ɓ��������B
�M�B���I�s�i2012�N�j�|�z�K�`�x�m�R�[�`�唒��|�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���̖ړI�̓z�V�`���o�l�Z�Z���A�A�J�Z�Z���Ȃǂ̎B�e�ł���B 7��22����9���߂��ɐV�⍑�w���o���A�����A���쌧��P�xSA�Œ��H�A7���߂��ɂ͈ɓ�IC���~�荂���̗щ��̑����ɓ������B ����ŃY�{�����r�b�V�����G�ꂽ�B �q���V�W�~�A�I�I�~�X�W�Ȃǂ̒��ɍ������āA�x�j�����}�_���K���ڂ��������B �ƂĂ�����������ł���B �������ӂł͍�N���l�X�W�{�\���}�L�`���E�A�t�^�X�W�`���E�A�~�X�W�`���E�A�z�V�~�X�W�A�V�[�^�e�n�A�N�W���N�`���E���̑������̒����m�F�ł����B ��N�ɔ�ׂă`���E�̌̐��͏��Ȃ��A���҂����������A�J�V�W�~�̎p�͌����Ȃ��������A�J���X�V�W�~�A�I�i�K�V�W�~�A�V�[�^�e�n�A�x�j�����}�_���K�Ȃǂ�����ꂽ�B ���Ɍ����������P���ł͎��Ԃ��x���������߂��A���ł̓E���M���q���E�����A�R�L�}�_���Z�Z�����炢�ŁA���̑������������悤�ȃ]�E���V�i�q���V���R�u�]�E���V�j���m�F�����ɂƂǂ܂����B �����߂��@�ɗѓ��ɓ���Ƃ��������E���W���m��������B�e����B ����ɐi�ނƃN�W���N�`���E�A�M���{�V�q���E�����A�R�����T�L�A�T�J�n�`�`���E�A�G���^�e�n�A���X�A�J�~�h���V�W�Ȃǂ�����A�X�ɐi�ނƍ�N�͏��Ȃ������c�}�W���E���W���m�������������B ���̃|�C���g�̋߂��̘e���ł͌F�ɏo��A�K���������̕��������Ă��ꂽ����⊾���������B �����ł̎B�e���I���A���Ԃɗ]�T���������̂ō�N�͓o��Ȃ��������}�R�i1955���j�ɓo�����B �R���t�߂ł̓L�A�Q�n���V��ł����ȊO�ɂ߂ڂ����`���E�͌�������Ȃ��������A����r���A�Ԕ��߂��̓o�R���ŐV�N�ȃG���^�e�n���B�e�ł����B ���͏��Ȃ����A�n�N�T���t�E���E�A���}�n�n�R�A�e�K�^�`�h���A�~���}�E�X���L�\�E�A�C�`���N�\�E�Ȃǂ̍��R�A��������ꂽ�B �V�C���ǂ��b���P�x����}�R����̒��ɂ��т��Ă����B �x�m�͌��Β��{���������C���߂���������ɖڎw�������̓����͂������B �Ⴄ�ђn�ɖ������ߑO���̔��������������A���̌セ�̔��̓���i�ނƁA���ړ��Ă̍L��ȑ������L�����Ă����B ����������n�߂Ă����ɑ����̃m�C�o���̉ԋz�����Ă����z�V�`���o�l�Z�Z�����������B �������̂ƌ͂ꑐ�͗l�Ȃ̂ł悭���Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B ���߂Č��钱�Ɋ������Ȃ���A�B�e���ς܂����B �����ŏo������l���A�g���t�V�W�~�ƃ~���}�J���X�V�W�~�َ̈�Ԍ���̂��������Ƃ����̂ŁA�ē����Ă��炢�B�e�����B ���̂����A���n�Œ��N�����������Ă���Ƃ����n���̕��ɏo��b���ƁA�ڕW�Ƃ��Ă����A�J�Z�Z����5�N�قǑO���p�����Ȃ��Ȃ����Ƃ̂��Ƃł������B ���̖�͉͌��ΔȂ̘V�ܗ��فu�R�ݗ��فv�ŏh�������B ���H�A�݂₰���̓X�Ŕ��������ς܂����̂����{�s�Ɍ����ďo�������B �r���A�唒��ѓ��ɗ������B �����ł́A�L�o�l�Z�Z���A�N�W���N�`���E�A���}�L�`���E�A�I�I�C�`�����W�A�L�x���^�e�n�Ȃǂ����ꂽ�B �[��5���߂��Ɉ��[���ɓ����A���ӂ�T���������A���Ԃ��x�������悤�ŁA���e�͏��Ȃ������B ���[�������������̕�������Ɋ������I1���̔�������A���̂܂܍��R�։������B 6�����߂��ɍ��R�s���ɓ��������[�H�̎��Ԃɂ͏��������̂ŁA���E��Y�́u���싽�v�܂ōs���Ă݂邱�Ƃɂ����B �n�}�Ō���Ɗό�����ɂ͎��ԓI�ɂ��肬��̋����ł���B �������A�������������܂ŗ����̂�����A�Ԃɍ���Ȃ��Ă��A�ƁA�R���⋋���ς܂��o�������B ���싽�ɒ������Ƃ��ɂ͊��ɓ��������Ă������A��}���œW�]��ɏ��A�X���[�V���b�^�[���g�����Ƃ����싽�炵�����i���ʂ��Ƃ߂邱�Ƃ��ł����B �@�@�@ ���łɏ��X�͑���X���Ă������A�X���܂��œ����t�߂ɂ����V�Ղ牮�̎�l�ɂ��肢���A3�l���̓V�Ղ������Ă�������B ��q����̘V�܂炵���A��l�́u��N�W�̓��������l�i�������̂��Ɓj�̗���X�v�Ǝ������Ă����B �C�����ǂ������̂��A�����ŋM�d�ȃC���^�P���T�[�r�X�ŐH�ׂ����Ă��ꂽ�B �������Ȃ���l�ł͂������B�r�[�������߂Ȃ��̂��c�O���������A�ڂ̑O�ŗg���Ă�������V�Ղ�͑�ς������������B ���s������2100�L���ɋy���A���̂��g���u�����Ȃ��A�C�̂��������u�ł̎B�e���s�ŁA�ō��̗��ł������B
�S�C�V�c�o���V�W�~�ώ@�L�i2013�N�j
�Ɨt�������т��\���钱�S�C�V�c�o���V�W�~�́A1973�N�ɌF�{�������S���㑺�̎s�[�R�Ŕ�������A�傫�Șb��ɂȂ�A�w�p�I���l����1975�N�ɂ͍��w��̓V�R�L�O���ɑI�肳�ꂽ�B ��������͂�2�N�œV�R�L�O���w�肳�ꂽ���Ƃł�������悤�ɁA���̋H�����͓��M���ׂ����̂ł���B ���̌�̒�������A����b���A�����x�A�ޗǂ̐�㑺�A�{�茧�̐{�ؑ�������������ꂽ�����ޏN�W�҂̈�@���l��X�є��̂Ŕ����㐔�N���o�����ĂقƂ�ǂ̏ꏊ�Ő�ł����Ƃ����B ���݁A����b���ƍ���s�����ƂɂȂ�s�[�R���c���ꂽ�����n�ł��邪�A�����ł�1996�N�ɐݒ肳�ꂽ��̕ۑ��@�w���Ƃ��Č��d�ɕی삳��Ă���B �ȑO���炱�̒���Ƃ�����S�C�V�c�o���V�W�~���̖ڂŌ��ĎB�e�������Ǝv���Ă������AGt����Əo�����邱�ƂɂȂ����B �Ő����͉߂��Ă����悤�����A�ی�ӔC�҂̕��ɖ₢���킹���Ƃ���A�܂��Ԃɍ����������Ƃ������Ƃŋ}�7��16���̑����o�������B ��B�����ԓ����o�R�����㑺�ɓ������̂�9���߂��A�r�����X�U�Ȃ���ړI�n�ɂ�10�������������B �h���\��̎s�[�ό��z�e���̌��l���B�e�ώ@�|�C���g���ē����ĉ��������B�@ �|�C���g�͎s�[�R�[�̌k�������ɂ���500�N�ȏ�͌o�߂��Ă���Ǝv����Ɨt������������T���Ƃ����i�ς̒n�ł������B �k�������ɂ̓A�T�q�i�J���g���{�������I�j�����}�����ܐ��Ă���A�q���n���[�~�̍��������ォ�畷�����Ă����B �ŏ��̊ώ@�|�C���g�̓P���L�̑�̒n��10����Ŗ{��̐H���ƂȂ�V�V���������������Ă���̂����������B �������n����ꏊ�������Ă���A������Ō��邽�ߎɂ��Ȃ葫�������s����Ȃ��߁A���������̐����ێ�����ɂ͍�������̂ňꎞ�Ԓ��x�Ŏ��̃|�C���g�Ɉړ������B �����͎R���������o�����Ƃ���ɂ���A�����тɕ���ꂽ�����Ȍk�������̑�̖�8����̕��ŁA�����ɂ��V�V���������������Ă���̂��m�F�ł����B ���炭�ώ@���Ă���Ə����Ȓ��e�����X���E�ɓ���悤�ɂȂ�A300�~���̖]�������Y�Ŋm�F�����Ƃ���ǂ����ړI��ł��邱�Ƃ��������B ���܃`���`������e��ǂ����߂Ȃ����ꎞ�Ԍo�߂����Ƃ���ŁC�_���Ή����̃��X�g�����܂ʼn��蒋�H�����˂ċx�e���A�Ăі߂��Ċώ@�𑱂����B �������̊Ԃؘ̖R����𗁂тȂ���`���`������͉̂��x���m�F�ł��������̓��͌��lj��̕��ɂ͍~��Ă��ꂸ�A���Ƃ��؋��ɂȂ���x�̖]���̎ʐ^�����B��Ȃ������B 10��������s�����J�n�������͑O���Ƒ傫���ς�炸�C���ԂŃ`���`����щ�邾���������B ���炭�t�߂��s������߂����肵�Ă����Ƃ���AGt���A�q���W�H���̉Ԃɋz���ɗ��Ă���̂��������B ���X���̂��遉�������B�������B�e����Ƃǂ����ɏ����Ă��܂������A����ʼn��Ƃ������̖ړI��B���邱�Ƃ��ł����B ���ꂩ�瑽���]�T���o�Ă��āA�H�ʂɗ���o�����ŋz������~���}�J���X�A�Q�n��L�^�L�`���E�A�~�h���q���E�����A�V�[�^�e�n�A�R�`���o�l�Z�Z���Ȃǂ��B�e�����B �R�����T�L�̍����^��������A�O�������g�Q�I�g���{���t�߂ɑ������邱�Ƃ����������B �ߌォ��́AGt����́A�_���Εt�߂�k��������T�����邱�Ƃŕʂ�A���́A�ł�������Ɨǂ��ʐ^���B�肽���ƁA���̏ꏊ�ō~��Ă���̂�҂��Ă����B 3�����߂��A�A�鎞�Ԃ������Ă��Ă��A���ǁA�߂��ɍ~��Ă͗��Ȃ������B ���߂āAGt����̂��鉺�̕��Ɍ��������Ƃ���A�o������Ď������A�������̋߂��Ō��������ƁA���ނ�������Ă��ꂽ�B �܂����邩������Ȃ��ƒT�����Ƃ���A�q���W�I���ŋz�����Ă���{�큊�������B �ߊ���Ă�������l�q���Ȃ��BGt����ɂ��g�тŘA�����A�����ł��炭�B�e�����B�߂���T���ƕʂ̌̂����������B �����̌̂́A��ɎB�e���Ă������ɔ�׃X���Ȃǂ��Ȃ��A�A��ԍۂɂȂ��Ă̑�q�b�g�ł������B 16�����߂�2���Ԃ̗\����I�����A�A�r�ɂ����B �����͂Ȃ��Ȃ��育�킢�����Ɗ��������A���ʓI�ɖړI���ʂ������Ƃ��ł��A�����̐��Ԃ������������ƂŖ����ł��鉓���ł������B ���̎Y�n�����ł��Ă������ŁA���n�ł́A�Ǝ��̊Ď��̐������A�n��������ĕۑS�����Ɏ��g��ł���ꂽ�o�܂�����B 2012�N�ɒn���̕������S�ƂȂ��āu�S�C�V�c�o���V�W�~�̋�������v�������������A����ē����Ă����������z�e���̌��l���a�l���͖{��̉�ł������B ���n��K��Ĉ�Ԋ��������Ƃ́C����݂̂Ȃ炸�n���������ĊĎ����̊F���A�n���̍��Y�����Ƃ������ʂ̔F���ň�ۂƂȂ芈���Ɏ��g�܂�Ă���Ƃ������Ƃ������B ���K�҂ɑ��Ă͊F�C�����悭�ڂ��Ă����A���L�̂��̂Ƃ��Č[������������Ă��邱�Ƃ͑�ϑf���炵�����Ƃ��Ǝ��������B
���̊ۍ�������J�c�����ցi2013�N�j
�܂��A�������������܂ŏo������̂�����A�A��r���A���̖����Ƃ��Ēm���Ă���J�c�����ɂ�����Ă݂悤�Ƃ������ƂɂȂ����B 7��10���A�l�b�g���Ԃ�Mn���I�I�E���M���q���E�������������Ƃ̂��ƂŁA�H�g����ē������ہA���̘b�������Ƃ���AMn�����7��17�����瓒�̊ۍ����ɏo������\��Ƃ̂��ƁA���̌��ʂ�m�点�Ă��炤���Ƃɂ����B ���̌�AMn����\��ʂ�~���}�����L�`���E�A�~���}�V���`���E���B�e�ł����Ƃ̏��Ƌ��ɁA�ڂ����|�C���g�������������������Ă����B �������́A7��29���A2�T�ԋ߂��x���̂ŁA���ꂪ�ǂ��e�����邩�Ƃ̕s�������������o�����邱�Ƃɂ����B 17���⍑���o���AGm����ƌ��݂ɉ^�]���A�r���x�e���J��Ԃ��Ȃ���A�����A8��30���A���̊ێR�o�R���ł���n�����̒��ԏ�i�W����1700m�j�ɓ��������B ���s������830km�B �����A�Q�������f��o��A��30�����Mn������̂����������i�W����1850m�j�ɒ������B �����́A�V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă����60�����̃����Q�c�c�W�̌Q�������邱�ƂŗL���ŁA6�����{����7���ɂ����Ă��S�y���R�����悤�ȍg�F�ɐ��ߏオ��Ƃ����Ă���B �Ԃ͊��ɏI����Ă������A�~���}�V���`���E�́A���\�������āA���A���A����A�Y���ȂǗl�X�Ȑ��Ԏʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B ���X�����L�`���E���ڂɕt���A���ɂ̓~���}�����L�`���E�Ǝv����̂�����A�������̎ʐ^���B�����B ���̂ق��A�q���E�����`���E�A�R�q���E�����A�M���{�V�q���E�����A�q���L�}�_���q�J�Q�ȂǑ����̒����B�e�ł����̂Ōߌ�͂�������ɂ��A�r�̕������Ɍ��������B ���̎��ӂ�2���ԋ߂��U�����A�����ł́A�����̃q���E�����ނ̂ق��ɁA�J�I�W���g���{�Ƃ����������g���{���B�e�ł����B ���̖�͏����s�̕z������ɏh�������B �Q�����f��o��n�߂��Ƃ���ŎႢ�������ォ��~��Ă��āA���m�ێR�ɓo�낤�Ƃ������A����������Ȃ������A�ꏏ�ɘA��čs���Ă��������A�Ƃ����̂ňꏏ�ɓo�邱�ƂɂȂ����B �r���AGm�����ɂ͏����ƂȂ�A�J�Z�Z���������A�܂��G���^�e�n�A�N�W���N�`���E�A�t�^�X�W�`���E�A�R�L�}�_���Z�Z���Ȃǂ����ꂽ�B �������߂���ƍŏ��͋}�ł��������A����Ɋɂ₩�ɂȂ�A��30���ŎR���i���2101m�j�ɒ������B �Ⴂ����������������Ƃ������Ă��A�v�����قǑ�ςłȂ������B ���̓��k��ɂ����A���n��T�������Ƃ���A���X�~���}�����L�`���E�����ꂽ�B�����X�����̂������������A�������B�e�����B �Ƃ܂�����Ԃł͗��������B��Ȃ��̂Ł�������ǂ������Ă���̂�_���Ĕ��Ďʐ^���������B�����B  3���ځA�n�������ӂ����炭�T��������A�J�c�����Ɍ��������B ������16���߂��܂ŒT�����A�A�J�Z�Z���A�X�W�O���`���o�l�Z�Z���A�E���S�}�_���V�W�~�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B ���̓��́A��ԎR�𐳖ʂɌ��邱�Ƃ̂ł���h�u�y���V�����r���[�����v�ŏh�������B  4���ځA�����߂��ɏh���o�����A�Ԓ����ӂ�T�������B �����ł͐V���Ƀ��}�L�`���E�A�~���}�J���X�V�W�~�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B �ړI�̃~���}�����L�`���E�A�~���}�V���`���E�̂ق��A�A�J�Z�Z���A���}�L�`���E�Ȃǂ��B�e�ł��A���ʂ̑傫�����������ł������B �N���}�c�}�L�`���E�B�e�L�i2014�N�j
2013�N�̎R���ނ��̉��A�N���c�L�ɏڂ���Kw����ɁA�ꏊ�⎞���Ȃǂ̏��������������Ƃ���A�ꏏ�ɍs���Ă��ǂ��ł���A�Ƃ������ƂŁA�ނ̓s���Ɣ������Ȃǂ��瓯�N6��4���ɐM�B�֏o�������B �V�C���̑������͈����Ȃ������悤�����A���ǂ��̎��́A�N���c�L�̎p���猩�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B ��2014�N�A���x��N�o�߂��`�����X������s�������Ǝv���Ă����Ƃ���A5��22���i�jKw����u���T���͐M�B�̕��A�V�C�͗ǂ����������A�������T���x�݂���ꂻ�����v�Ƃ̘A���A��Ԏ��ł��̓��̖�o�����邱�ƂɂȂ����B �V�⍑�w�ŗ������A�ŏ��̖ړI�n���A��r�I�ʐ^���B��Ղ����낤�ƕx�R���ʂɐݒ肵21�������̉^�]�ŏo�������B ���s���߂��փ���������ŁA������Ɍg�тœV�C�\����`�F�b�N���Ă���Kw���A�u�����A�k�̕��͂��܂�V�C���ǂ��Ȃ��������v�Ƃ������ƂŁA�ړI�n���A���v�X�ɕύX���������ɓ������B �x�e�A�����Ȃǂ��Ȃ���A����7���߂��ɍŏ��̖ړI�n�t�߂ɓ��������B �����͔�r�I�W�����Ⴍ�A����̎R�̐��������A�����x����������Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̖ړI�n�Ɍ������B ���Ɛ��L���n�_�Ɂu���H�����Ă���ʍs�~�߁v�̗��D�A�����ł���Ɏ��̖ړI�n�ɕ����]���������A�������u�o�R�҂̊F�l�ցv�Ƃ������D�A�o�R��������Ă���ʍs�s�\�Ƃ̂��ƁB �F�l���畷���Ă���������̏ꏊ�́A���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA��A���v�X�́A�f�O������Ȃ��ɂȂ����B �����̕x�R�ɓq���āA�����́A������ł��̑��̒��ł����悤�A�Ƃ��炭�E�X�o�V���`���E��c�}�L�`���E�A�g���K�Ȃǂ�ǂ������Ďʐ^���B���Ă������A�ӂƂ��ꂩ��s�������ȏꏊ�Ƃ��ăl�b�g�Ō����咬�s���̖��O�������B ������s���Ă��ߌ�ɂȂ�A�k�̕�������V�C���ǂ����킩��Ȃ����A�_�����Ƃōs���܂��傤�Ƃ������ƂɂȂ�咬�����ďo�������B���ł�10���A�⍑���o�����Ă���700�L���ȏ㑖���Ă����B�@�@ �����ɐ��ɓ����B �ꏊ��ς��悤�ƁA���ԏ�Ɍ������Ă����Ƃ���A�ڂ̑O�𔒂������������B �X�W�O����������Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�M�B�̃X�W�O���̎ʐ^�ł��B�낤�A�ʂ̋C�����Œǂ������čs�����Ƃ���A���[�ɂƂ܂����B �]���Ŕ`�����Ƃ���u�N���c�L���I�vKw������삯���A�����ɔ�ї����Ă͂Ƃ܂�̂�ǂ������Ȃ���ʐ^�Ɏ��߂��B ���ł͂Ȃ����A���Ƃ��ړI�B���ł���B ����ŗ��������Ē��H�ł��H�ׂȂ���҂��Ƃɂ��A���炩���ߔ����Ă������ٓ��������A���̃|�C���g�߂��ŁA���ɕ����ꂽ�B �ٓ����J�����Ƃ��Ă����Ƃ���A�Ί݂ɍs����Kw����菵���A�}���ŕٓ��ƃJ�����������ċ삯�����Ƃ���A�N�₩�ȃI�����W���ڂɔ�э��B���Ԃł͏��߂Č���N���c�L���ł������B �N���c�L�́A���ܑ���̏�ŋx��A�~���}�X�~���ŋz�������肵�āA���̂����ǂ����ɏ����Ă������B ���̓��܂����x�����ꓯ���悤�ȍs�����J��Ԃ����B ���̓x�ɃJ�����������Ēǂ������A���Ƃ��[���̂����ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B 14���߂��ɗF�l��Gm����A���̎����q���M�t�`���E�����ȍ����Ō�����Ƃ̓d�b�������������B ���ԓI�ɒx���������A�N���c�L�͊��\�����̂ŁA�s�������s���Ă݂悤�ƁA����s�Ɍ��������B �������̂�17���߂��ŁA�������Ƀq���M�t�͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �N���c�L�B�e�͂ł����̂ŁA�����́A�\�肵�Ă����x�R�͎~�߂ɂ��A���ʂŁA�V���ȏꏊ��T�����Ƃ������Ƃɂ����B ���K�ŏh��\�A�߂��̃��X�g������21���߂��ƒx���Ȃ����[�H��ۂ�j�t���������B �⍑�o������1060�L�������Ă����B �����́A����ˉ��Ɍ������AKw����́A�N���c�L�̐V���Ȑ����n�T���A���́A�z�~��Ȃǂ��̑��̍����̎ʐ^�ł��B�낤�ƁA�V�䍂���[�v�E�F�C�w���ԏ�ɎԂ��߁A�ʏ̍��җѓ��֓������B ���炭�́A�����炵�������ɂ͏o���Ȃ������B �ѓ��e�̐�̗�����k�A�萁���n�߂��V�A�R�쑐�����Ȃ���������Ɛi�B �͂��Ɋ��ނ��A�Ђ���Ƃ��������C�����ǂ��B �ꎞ�Ԃ��炢�������Ƃ���ʼn��������ȐԂ��ۂ����̂����ł���̂��ڂɓ������B �R�c�o���ł́A�Ȃ����������A�ƒǂ������Ă���ƎB�e�����̂͏����ȃK�ł������B ��ɁA�F�l��Om����u�J�o�V���N�v�ŁA���̎����ɂ��������Ȃ����\��������Ƃ̘A���������������B �ѓ��ɗ��ꍞ��ł����k������A�X�ɐi�ނƁA�L�x���^�e�n�A�R�q�I�h�V�A�N�W���N�`���E�Ȃǂ̉z�~���R�c�o���A�T�J�n�`�`���E�A�x�j�V�W�~�Ȃǂ����ꂱ�����B�e�����B �@�@�@ 17�����[�H��ۂ�A��������ł��炭�x�e������A�r�ɏA�����B �x�e�A���������Ȃ���A�������o���n�_�̐V�⍑�w�ɓ����B�S���s������2000�L���̎B�e���s�ł������B
���́A���d�R�����ɂ͒��̎B�e�ł͉ߋ�3��K��Ă��邪�A��������H�ŁA��x�͂��̎����ɍs�������Ǝv���Ă����Ƃ���A�F�l��Kn����A�ꏏ�ɍs�������Ƃ̘b������A��l�ōs�����Ƃɂ����B 5��7���A������`����̒��s�ւŐΊ_��`�ɓ߂��ɓ����A�����^�J�[����āA�悸�߂��̃o���i�����Ɍ��������B �ԏ�ɍs���ƁA�x�j�����A�Q�n�A�����E�L���E�~�X�W�A�I�I�S�}�_���ق������̓썑�̒����o�}���Ă��ꂽ�B �[���܂ł����ʼn߂������̂��A��h�ɂ��Ă���z�e���~���q���Ƀ`�F�b�N�C���A�������I�����B ��8���A�{���̃A�T�q�i�����߂ĉ��Γo�x���ʂɌ��������B �A�T�q�i�̔����n�́A���Γo�x�R���t�߂ŁA�ȑO�͔����܂œo��Ȃ��ƌ����Ȃ��������A�ߔN�A�[�̕��ł����\������悤�ɂȂ����ƕ����Ă����B ���̓��́A�F�l���畷�����^�h���t�߂̘[�̕���T�����A����������Ȃ���A�����͓o�R�̗\��ł������B ���G���}�T�i�G�Ȃǂ̃g���{�ȂǎB�e���Ȃ���ѓ���i�ނƁA�����ɂƂ܂����A�T�q�i���A���̓��Z���_���O�T�ɂƂ܂����̂����������B �����Ȃ�̖ړI�B���ł���B ���̗ѓ��ł��炭�߂�������A�약�Ɍ��������B�����͐Ί_���ł͋��w�̊ό��n�ł��邪���̃|�C���g�Ƃ��Ă��m��ꂽ�Ƃ���ł���B ���炭�T��������AKn����͏��߂ĂƂ������Ƃ������̂ŁA�ό����A�Ƃ������ƂŐ약�p�̍��l�̕��ɏo�Ă݂��B �G�������h�O���[���ɋP���p���͉��Ƃ��������A���炭���߂Ă������A�ӂƍ��l�e�̑��n������ƁA�Z���_���O�T�ŋz����������̃L�~�X�W���ڂɓ������B ����܂łɌ������Ƃ������ł��邪�A��������̏�̕��ɂƂ܂��Ă���悤�Ȃ��̂���ŁA���̂悤�ɉԂɂƂ܂����̂͏��߂Ă������B �ǂ��ʐ^���B�ꂽ�B ���ɎR���Ɍ������A�������Ƃ���ɂ��郌�X�g�����ŁA�C�����Ȃ���S�[���`�����v���̒��H���ς܂��A�߂��̃|�C���g�ɓ������B �Ԃ��߁A�~���Ƃ����ɃA�T�q�i���ڂɓ������B���������́A����ȂƂ���Ō�����Ƃ͋����ł������B �t���ԂɁA�����J�����������A���낢��Ȏʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B���̑��R�m�n�`���E��N���e���V���`���E�ȂǓ썑�̒�������ނ��B�e���A�o���i�����o�R�Ńz�e���ɋA�����B �^�ߍ����ł́A2���؍ݗ\��̂Ƃ���Z����1��������]�V�Ȃ����ꂽ���A�������ŗ^�ߍ��̗F�l��Sj����̏���������A�^�C�����A�T�M�}�_�����B�e�ł����B�@ ���̌�Ί_�o�R�Ő��\���ɓn��A2���ԒT�����A�������I�������B ����̎�ړI�ł������A�T�q�i�ɂ͐��\���ł��o����Ƃ��ł��A���̑��A���̎����ɗ\�z������ɂ��Ă��啔�����B�e�ł����B ���̐���71��ł������B
�E�X�o�L�`���E�����߂Ėk�C���Ē���L�i2014�N�j
���̒����A��ʂɔN��1�`��������̂ɑ��A�{��́A1�N�ڂ͗��̏�Ԃʼnz�~���A���N�z�������̔N��匉������̏�Ԃʼnz�~���A���N�̉āA����3�N�ڂɂ悤�₭�����ɂȂ�Ƃ������قȐ��Ԃ̒��ł���B �����Ō�����̂́A5�����{�`7���Ɍ��肳��邱�ƂȂǂ���A���̌���ꂽ�����ɂ������o�R�ƂȂ�Ǝ����ɂ͌��邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ǝv���Ă����B ����Ȓ��A�l�b�g�Œm�荇���ɂȂ�����R�s��Mn����A���ē����܂���A�Ƃ����A���������������B Mn����́A��w����ɕS���R�j�����Ƃ����o�R�ƂŁA�k�C���ɂ͖��N����͒ʂ��Ă����A���Ȃǂ̎ʐ^�́A���̍��ԂɎB���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B ���́A�k�C���ɂ�2009�N�ɒ��B�e�ړI�ōs���A����ɂ��Ă͐�Ɍf�ڂ��Ă��邪�A���̎��͓V�C�������A�\��̔������炢���������ł��Ȃ��������Ƃ�����A�E�X�o�L�`���E�ȊO�ɂ����Ă��Ȃ��킪�����̂ŁA����ł͐���Ƃ��A�Ƃ��肢�����B �����l�b�g���Ԃ̔����s��Ms������s�������Ƃ̂��Ƃ������̂�3�l�ōs�����ƂɂȂ����B �O��Ƃقړ����R�[�X�Ŏ����v�悵�AMn����Ɏ蒼���Ȃǂ��Ă�������B�@ �o���́A�E�X�o�L�`���E�̔��������ɂ��킹��6��25���Ƃ����B����Ms����́A�L����`�����ɏo�����A�V���`�ɂ�10���߂��ɒ������B �����Ƀ����^�J�[����z���A�班���x��ē������ꂽMn����ƍ������A�ŏ��̒T���n�����R�n���������B �O��́A�V�C�������A���邾���ɏI�������C�I�쉈���̗ѓ������[���i��ł������B�G�]�V���`���E�A�R�q�I�h�V�A�V�[�^�e�n�Ȃǂ����X�ƌ���A������B�e���Ȃ���i�ނƁA�t�L�̗t��ŋx�ރJ���t�g�^�J�l�L�}�_���Z�Z���́��ɏo������B ���߂Č����ł���B�����ā�������A�B�e����B ���̌�A��������߂Ă̎�ł���z�\�o�q���E�������B�e�ł����B �قړ������I���A�����̏h���ꏊ�ł���эL�Ɍ��������ƎԂňړ��r���A�^�]���Ă������́A���ƂȂ��\�������āA�Ԃ��ߋ߂���T�������Ƃ���AMn�����̃K�P�ɂƂ܂��Ă���G�]�c�}�W���E���W���m�����������B �ŏ��̏ꏊ�ł́A�{�킪������Ƃ̂��ƂŁA���ӂ��ĒT���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ɁA���Ȃ�͂��ꂽ���̏ꏊ�Ō��邱�Ƃ��ł����̂ł���B�K�^�ł������B�z�e�����q�m�[�X�����h�эL�ŏh�����A�����́A�莺�������勫�Ɍ��������B �����ł́A�z�\�o�q���E�����A�I�I�C�`�����W�Ȃǂ̑��A��10�����̃~���}�J���X�A�Q�n���W�c�z�����Ă���̂ɑ������A�������ɖk�C���A�Ƌ������B ���Ԃɗ]�T���������̂ŁA�O���\�肵�Ă��Ȃ��玞�Ԃ��Ȃ����Ȃ������������̃W���E�U���V�W�~�|�C���g�ɍs�����Ƃɂ����B �����������A��ɗ��Ă����l���A�̖̂ʉe�͖����Ȃ��Ă���A�����ɂ͂��Ȃ��A�Ƌ����Ă��ꂽ�B�d�����Ȃ��̂ŁA�߂��̎����悤�Ȋ��̂Ƃ���֍s���A�T���Ă݂��B �V���I�r�q���q�J�Q�Ȃǂ��B�e���A�A�낤�Ƃ������AMs���A�����������̂����ł��܂��A�Ƃ����̂ł��̉e��ǂ����B �u�W���E�U���V�W�~�I�v�B �����勫�ŏo������l����A�W���E�U���V�W�~�̓s�[�N���߂��Ă��茩��͓̂���ł��傤�A�ƌ����قƂ�ǒ��߂Ă�����ɉ���Ƃ��ł����̂��B ���ꂩ��эL�Ɉ����Ԃ��A�Ō�ɐ쐼���t�߂�T�������B �O��A�E���W���m����J�o�C���V�W�~�������ꏊ�ł���B ����́A�����͌�������Ȃ��������A�����̃A�J�}�_����R�L�}�_���Z�Z���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B ���̓����O���ɑ����эL�̃z�e���ɔ��܂����B �����́A�O�\���낢��Ȏ�ނ����邱�Ƃ��ł��A�����Ɋ��҂��Ă����ꏊ�ł���B ���Ɍ������������ӂ����l�ŁA�ȑO�Ƃ́A�����ς���Ă���A���ʂɌ������ނ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B ���̓��͂����������ʂ��Ȃ��A�\���쉷��̍���z�e���Ƀ`�F�b�N�C���������A�����ł́A3���߂�������傫�ȃq�O�}�̔������o�}���Ă��ꂽ�B 5���ځA����̉����̎�ړI�n�ł���w�_���Ɍ������B �r���A�唟���ԏ�t�߂ŋL�O�B�e������A�j�Z�C�`�����}�b�v�ѓ��ɓ���B Mn���ѓ����ԋ�������Ă���ꂽ�̂ł��Ȃ艜�܂ŎԂœ���A��������T�����n�߂��B ���ɐV���Ȏ�͌�����Ȃ��������A�����̒��ɏo����Ƃ��ł����B ���̓��́A�k�C���̒��̏������낢�땷����Ƃ����w�_���̃y���V�����R�̏�Ŕ��܂����B ���ʂ�ɁA�V�����J���t�g�q���E���������邱�Ƃ��ł������A���̑������̒��ɉ���Ƃ��ł����B �r�����قǂ����k�́A���Ȃ�}�ΖʂŁA�������点�����ςȂ��ƂɂȂ�B �X�g�b�N�ł�������x���A���������݂��߂Ȃ���T�d�ɑ���i�߂��������A�X�ɓo����8���߂��ɖړI�n�ɓ��������B �r���ō��R�A���Ȃǂ��B�e���Ȃ���������o��������������A�v�����قǔ��Ȃ������B �@�@�@ �R�}�N�T���́A�V�������K������Ă���A��������͂ݏo�����Ƃ͋�����Ȃ��̂ŁA�]���ł̎B�e�����\�����Ȃ����B ����Ƃ��A�����s�[�N���߂��Ă����悤�ŁA�X�������̂������������A���Ƃ��ʐ^�Ɏ��߂邱�Ƃ��ł����B �A�T�q�q���E���������҂���������͌����Ȃ������B �]�T���o���̂ŃR�}�N�T�ȂǎR�쑐�̎B�e�������B���̓��A�_���o�Ă��āA�����p�������Ȃ��Ȃ����̂ŁA���߂ɉ��R�����B ���̌�A�y���V�����ŕ����Ă����I�I�C�`�����W�|�C���g�ɍs���Č����Ƃ��둽���̃I�I�C�`�����W�����ċ������B����̃E�X�o�L�`���E���B�e�ł��A�܂������̃I�I�C�`�����W�������đ喞���̈���������B �O��Ƃقړ����悤�ɂ��낢��Ȏ���B�e�ł����B ���̓��̏h���͏\���x�A�������ɂ��鐁�㉷��ŁA�����̉���͂���܂łōō��Ǝv����قǑf���炵������ł������B �����̒��ɍ������āA����܂Ō��邱�Ƃ̂ł��Ȃ������J�o�C���V�W�~�������邱�Ƃ��ł����B�@ ����炵���̂����Ă��̓s�x��Ԃ��A��������J���X�V�W�~�ŁA�����S�V�W�~�͂��łɃs�[�N���߂��Ă����悤�������B
�M�B���I�s�i2015�N�j�|�q���M�t�`���E�B�e�L�|
�߂�����́A�c��ɋP����ԎR���]�܂ꂽ�B ������ڂ́A�������ӂ̃q���M�t�`���E�̒T���ł���B
�����ł́A���̑��A�X�W�O���V���`���E�A�c�}�L�`���E�A�V�[�^�e�n�A�����^�e�n�A�~���}�Z�Z���Ȃǂ��B�e�����B
�ٓ����H���ς܂��A�ߌ�́A���̑��̃q���M�t�`���E�A�q���V���`���E�|�C���g�����ӏ�������Ă݂����A���Ǘ���Ƃ����邱�Ƃ͂ł����A�ߍ@�l�����ɂ́A�h�ɂ̓��}����YH�ɓ������B
���̏h�ɂ́A���߂Ăł��������A�������Y��ŁA�H�����ǂ��A�܂��A��������͐��ʂɔ����x�S�i���]�߁A�Ȃ��Ȃ��ǂ��z�e���ł������B
�O���ڂ́A�`���}�_���Z�Z���̎Y�n�Ƃ��Ēm���Ă���x�m�R�̖k���R�[�Ɍ��������B �k�C�������L�i2016�N�j
7�����A���̓��͈ړ����ŁA�x�ǖ쐁�㉷��Ɍ������B�r���A�O��W���E�U���V�W�~�������������߂��̃|�C���g�Ɋ���Ă݂����A���̎p�͂Ȃ������BR274���X�ɐ��ɐi�݁A������C�I�쉈���̗ѓ��ɓ������B�r���A���N�k�C���Œ��̊ώ@�𑱂��Ă���Ƃ����l�ɂ������̂ŁA�b�����Ƃ���A���N�͂���܂łɂȂ��قǐ������Ȃ��A�����Ȃ���������Ƃ̂��Ƃł������B���̗ѓ��ł́A�O��́A�����̎������ꂽ���A����͏��Ȃ��A���̘b�������������A����ł��A�G�]�c�}�W���E���W���m�����̑��A�k�C���Y�̑�\�I�Ȓ������킩�B�e�ł����B
10�����A�[�t�B���X�̊J���ʐ^���B�낤�ƁA6���O�ɉ���ɐZ����A���H�͕ٓ�������Ă��炢�o���A�O���̃J�V���тɌ��������B�k�C���̒��͑����A���ɔ�яo���Ă���̂��������A�J�V����@���ƁA�n���V�~�h���V�W�~�����ɍ~��Ă��āA���炭�҂��ĉ��Ƃ��J���ʐ^���B�ꂽ�B���̑��E�X�C���I�i�K�V�W�~��E���~�X�W�V�W�~�Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B�E���~�X�W�V�W�~�́A�Ɠ��̔�������̂���V�O�i�^�^�ŁA���߂Č����ł������B
�M�B�����L�i2016�N�j-���R�������߂�
7��21���i�j���@ 7��22���i���j�J�`�܁`��
�㍂�n�ւ̎��Ɨp�Ԃ̏�����͋֎~����Ă���̂ŁA�^�N�V�[�ŏ㍂�n�̓o�R�o���_�Ɍ��������B���悻15km�A25���̍s���ł���B�r���A�吳�r�Œ�Ԃ��A�L�O�B�e������B�����ɕ�܂�Ă����吳�r�̏���_�Ԃ��䍂�A�������B 5�F55�㍂�n�o�X�^�[�~�i�������B�^�[�~�i���L��Œ��H��ۂ�A�o�R�̎x�x�A�g�C�����ς܂��B���ݕ��̕⋋���s���A6�F15�^�[�~�i�����o�������B 6�F30�͓�����n��A6�F40�x�����A6�F45�o�R���ɓ����A�̂�����D�̎B�e���a�ƂȂ����B�����ɓo�R�J�n�A����ɂ͍������������т��A�̍��������̓o�R����i�ށB��7�W���i7���ڂłȂ�3���ځj�ŋx�����X�ɓo��B
No3�W���߂��̑��n�ŁA�N���}�x�j�q�J�Q�ƃ^�J�l�L�}�_���Z�Z���������艽�Ƃ��؋��ʐ^���B�e�ł����B����̉����ł́A�^�J�l�L�}�_���Z�Z������ڕW�ɂ��Ă���A�N���}�x�j�q�J�Q�́A�����I�ɂ���������̂悤�Ȃ̂ł��܂���҂��Ă��Ȃ��������A����Ɉ�x�ɏo������ƂŊ�т͔{�������B
14�F15 ��5�W���ʉ߁A15�F40�x��o�R���A16�F00�͓����ɂ��ǂ蒅�����x�~�A���X�ŗ₽�����ݕ��Ŋ������m�h���������B�㍂�n�o�X�^�[�~�i���Ń^�N�V�[�ɏ��A16�F50��n���ԏ�ɓ����B���������ς܂�17�F00���{�s���̃z�e�������o�������B
7��23���i�y�j�܁`���A28���`25��
10�F30������IC�߂��̃t�����[�K�[�f���ɓ����B�����́A�ȑO�����̒��������|�C���g�̋߂��ł���A��������̂ł���B�t�����[�K�[�f���ɂ́A�����̉Ԃ��A�����Ă���A�����ł́A�z�V�~�X�W�A�L�^�e�n�Ȃǂɍ������āA�N�T�t�W�ŋz�������q���V���`���E�ɏo����B�܂�������������Ŕ����Y��Ȍő̂ł������B�{��ɂ��ẮA����܂ŗ����ʐ^���B���Ă��Ȃ������̂ŁA�����I�ɂ͂܂��Ǝv���Ă������Ƃ����芴�������B�����ł�1�Ԃ̎��n�ł������B 12�F00�~���}�V�W�~�̏���������F���̐_�{��قƂ�̌����ɓ���B�������A�����͂��ꂢ�ɑ��������Ă���A���n���قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă����B���炭�߂��̑��n���T�������A���̎p�͌�������Ȃ������B13�F00���쌧�x�m�������̉w�Ӗ؏h�Œ��H��ۂ�����A�A�J�Z�Z���̏��̂������������Ɍ��������B
7��24���i���j�܁`���`�܁A20���`24���`27�� 9�F00���쌧����ɂ��A���̖ړI�n�R�������������B9�F15���������ԓ��E�z�KIC�A10�F35�匎JC�o�R��10�F55�R����IC���~���B�����q���҂�x�m�g�c���ʂɖ߂�r���ɕx�m����̗��㎩�q�����Ԓn������B�{�݂ɂ͓���Ȃ����A�L��ȉ��K���y�A���j���ɂ͈�ʎs���ɉ�����Ă���B �{���ΔȂ̃��X�g�����Œ��H��ۂ�A�ȑO�z�V�`���o�l�Z�Z�����B�e���������ɓ����Ă݂��B�ȑO�ɔ�ׂāA���̎p�͏��Ȃ��A�قƂ�ǒ��߂����Ă������AGm����A��������A�z�V�`���o�l�Z�Z���A���}�L�`���E�Ȃǂ��B�e�ł����B
7��25���i���j �哌�������L�i2016�j
�����ɂ͑����̌Ώ�������A���̂��߃g���{������̉����ړI�̈�ł��������A����n�̃E�~�A�J�g���{�́A���\�������邱�Ƃ��ł����B
���̌�A����������T���������A�n�}���}�g�V�W�~�ɂ��ẮA�C�k�r�����Q�����Ă���r�n2�ӏ��Ŋm�F�ł����B�܂��A����̂��铇�̍ō����R(74m)�ł́A�{���ł͖����ƂȂ郊���E�L���E�����T�L�����邱�Ƃ��ł����B ����̉����̏o�����ɁA����Ⴄ�`�Œʂ�߂����䕗17���́A���̌��^�����A��p�ɏ㗤���傫�Ȕ�Q��^�������A28���ɂ͎��̑䕗18�����������A������ʂɌ������Ă����B 9��30���i���j�`10��2���i���j �k�C�������L�i2017�j-�t�̒������߂�-
�����A������҂��Ă��Ԃɂ͂Ƃ܂�C�z���Ȃ��̂ŁA���̏ꏊ�̎m�ʎs������̗ѓ��ɍs�����Ƃɂ����B���ӏ����s���A������̏ꏊ�ł����̌��邱�Ƃ��ł������A�ԂȂǂ͂Ȃ���щ�Ă���A���X�A�n�ʂɂƂ܂�̂��B�e����ɂƂǂ܂����B�����ł͂��̑��X�M�^�j�����V�W�~�A�G���^�e�n�A�N�W���N�`���E�A�R�q�I�h�V�A�R�c�o���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����B
���߂��Ȃ����̂ŁA���ʒ����S�n�ɖ߂�A�ٓ��B���A��͂�Ԃ��ǂ��ƍŏ��̏ꏊ�ɍs�����Ƃɂ����B�����ł́A���̓��A�^�ǂ���1�����A�J�^�N���ŋz�����n�߁A�O��̎ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B
���̌�A���R�k�ɍs�������Ƃ��b���Ă������A�قږړI�͒B�����Ă��܂������A�C�����������Ă����̂ŁA3�������ɂ͏I�����w�_���̏h�ɖ߂����B
�C�����Ⴍ�A�����͂��܂�ǂ��Ȃ����A1���ڂɑ�����X�̐��ʂŁA���̖�́A���������r�[���𖡂키���Ƃ��ł����B
�Ζk�����z������A�����A���̍ŏ��̃|�C���g�ł́A�C�����Ⴂ���Ƃ�����A�G�]�X�W�O���V���`���E1�������������ł������B
�O��A�`���}�_���Z�Z����1���̏W�����Ƃ����l�́A�^���|�|����������ꏊ�ŁA����ɂƂ܂��Ă���̂��̏W�����ƌ����Ă���ꂽ�̂ŁA���̏ꏊ�ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B1���ڂɂ́A�n�ʂɂƂ܂����̂����B�e�ł��Ă��Ȃ������̂ŁA����悭�A�ԂɂƂ܂����̂��B�肽���Ƃ̎v������ł���B�����ɂ͒��߂��ɓ����A�m���Ɉ�ʂɃ^���|�|���炢�Ă���A���҂��Ȃ��璚�J�Ɍ��ĉ�������A���̎p�͂Ȃ������B
�����̃|�C���g�͋߂��������̂ŁA�O���̏W�҂������Ƃ������ƂŊ��҂͂ł��Ȃ�������������x�s���Ă݂邱�Ƃɂ����B�����Ɍ����ꏊ���s�������Ă��邤���A�n�ʂɂƂ܂��Ă���1�����ڂɓ������B�C����8���Ɗ������Ƃ�����A�قƂ�Ǔ����Ȃ��̂łȂ��Ȃ��킩��ɂ��������̂ł���B�F�l�����ɒm�点�A���炭������B�e������A�_�����ƂŊd�������Ƃ���^�ǂ������߂��̃^���|�|�ɂƂ܂�O��̎ʐ^���B�邱�Ƃ��ł����B
���ɁA�X�ɓ쉺���A����܂Ő���K�ꂽ���Ƃ̂��钷���}���ѓ��ɗ���������B���炭���ĉ�������A�܂肪���ɂȂ������Ƃ����蒱�͂قƂ�nj��邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ŁA���ԓI�ɂ͑����������A�h���\��̑эL�s�̃z�e�����q�Ɍ��������B
���̓��͔������A�����͂���قǗǂ��Ȃ��������A�H����������̃W���E�U���V�W�~�A�ԂɂƂ܂����`���}�_���Z�Z���̎B�e���ł������̂�������ł������B
4���� �쑐���ł́A�I�I�o�i�m�G�����C�\�E����ʂɍ炫����Ă���A���̒��ɁA�j�����\�E�A�V���l�A�I�C���̑������̖쑐�����邱�Ƃ��ł����B�����ł͖쒹�����������A�L�r�^�L�A�S�W���E�K���A�A�I�W�Ȃǂ��B�e�����B
�����\�肵�Ă����`���}�_���Z�Z����W���E�U���V�W�~�́A����Ƃ��ړI��B�����Ă���A�C���I�ɂ͗]�T�ŁA���Ƃ͖����̈���ł�����������Ȃ�ɏ[����������������B
���̓����эL�ŏh�������B
5����
�悸�A�G�]���X������Ƃ��Ēm���Ă��鉹�X�_�Ђɗ���������B�����͖쒹�������A���X�̂ق��ɃA�J�Q���A�I�I�����A�V�W���E�J���Ȃǂ��B�e�����B ���ɁA���̂������D���여��̃|�C���g�ɗ���������B�������A�����͍�N�̑䕗�̉e���ŁA�P���R�����Ă���A���ɂ͊��y���A�|�ꂽ�Ȃǂ��c���Ă���A�V���Ԃ��ǂ��Ȃ��������Ƃ��d�Ȃ�A���̎p�͑S�������Ȃ������B�����ɐ�グ��Ɍ������B �r���A�V��͂܂��܂������Ȃ�A���X�J��������悤�ɂȂ����B����ł͒��͑S���]�߂Ȃ����A��̂��Ƃ��l���A�l�b�g�Œ��ׂ����ʒ��A�L�����̃|�C���g�ɗ������A�X�ɁA���������ɂȂ邪�A�ݏ֖��ɂ��A���������̋@�����ƁA����������B�ݏ֖��́A�����������ƂŒm���A���q���q�̉̂ɂ�����Ƃ���A���̓q�����q�����A�g�͂ǂ�Ԃ肱�A�X�ɃK�X���������Ă���A�قƂ�lj��������Ȃ������B�̊��C���͗뉺�ł͂Ǝv����قNJ����������i���ۂɂ�6���j�A�̎��̐Δ�Ɩ��\���̑O�܂ŕ����ċL�O�ʐ^���B��A���X�ɂ�������ɂ����B
�l���ɂ�4�����ɓ����A�h�ɂ͏��������̂ŁA������̊ω��R�����ɍs���Ă݂��B�V���������ɂ́A�J�^�N���A�j�����\�E�A�I�I�o�i�m�G�����C�\�E�Ȃǂ���ʂɍ炢�Ă���A������B�e���Ȃ��玞�Ԃ��߂�������A5�����ɏh���\��̃v���U���{�X�ɗ����������B���̏h�́A�������݁i2F���h�j���Ă���A�[�H�͓X�̋q�ƈꏏ�ŁA�Ȃ��Ȃ��ɂ��y���ł������B���̓��́A�����̃A�|�C�x�o�R�ɔ����āA�������Ԃɏ��������B
6����
�A�|�C�x�́i�ȉ��E�C�L�y�f�B�A�����j�A�l���S�l�����������R���x�Ő�����[�Ɉʒu���A�ꓙ�O�p�_�ŕW��810.5m�B�R�̖��̗R���̓A�C�k��́u�A�y�E �I�E�C�v�i�̂���Ƃ���j�ł���B�R���u�y����S��v�ƌĂ�Ă��邩�����łł��Ă���A����Ȏ��R�̌n�ƂȂ��Ă��邱�Ƃɂ���A1952�N�ɍ��R�A ���т��u�A�|�C�x���R�A���Q���v�Ƃ��č��̓��ʓV�R�L�O���Ɏw�肳�ꂽ�B1981�N�ɂ͓����R���ݏ֍�������̓��ʕی��ƂȂ����B�C�݂���킸��4�L���ɂ��т���A�|�C�x�́A�C����̔Z�������������߁A�C����ቺ�����A2000���[�g�����̍��R�Ɠ������������o���Ă���B���ӂ́u�y���J��������́v�ƌĂ�A�}�O�l�V�E����S�𑽗ʂɊ܂J��������ō\�����ꂽ����Ȓn���ł���B�����Z���Ɠ���n���̉e���ɂ��A�u�֖��A���v�����炷�鍂�R�A���̕�ɂƂ��ėL���ŁA80��ȏオ�m�F����A�Ԃ̕S���R�ƂȂ��Ă���B���E���ł����������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��ŗL�A ������������B
7�����ɏh���o���A�A�|�C�x�W�I�p�[�N�r�W�^�[�Z���^�[�O�ɒ��ԁA�o�R�͂��o���A8���ɓo�R�X�^�[�g����B���X���[�̃G�]�I�I�T�N���\�E�A�q���C�`�Q�A�~���}�X�~���Ȃǂ��B�e���Ȃ������i�߁A9���߂���5���ڂ̏����ɓ��������B�����܂ł͔�r�I�y�ŁA����Ȃ���v�Ǝv���Ă������A���ꂩ�炪���������B�}�ȓo��̘A���ŁA�q���`���}�_���Z�Z����������Ƃ���7���ڔn�̔w�ɒ����̂ɖ�40�������������قڌ��E�ł������B��l�̗F�l�́A�o�R���ꂵ�Ă��āA����قǔ�ꂽ�l�q�͂Ȃ��A����Mn����́A�R���܂ōs���Ă��܂��ƁA�o���Ă������B
���̓��́A�эL�ŏh�����邱�ƂɂȂ��Ă������A�V�C���ǂ��A���Ԃ�����̂ŁA���߂ɉ��R���A������������ꏊ�ɗ�����邱�Ƃɂ����B12���Ƀ|�C���g����ɂ��A1��20���ɂ͓o�R���ɓ����A�g�C���x�e�������Ƃ����ɂ������o�������B
6���� ����őS�������I���A�V���`����q����ōL����`�o�R�A��11���O�Ɏ���ɓ��������B
����̉����́A�O���A�k�̕���������r�I�V�C���ǂ��A�G�]�q���M�t�`���E�A�`���}�_���Z�Z���A�W���E�U���V�W�~���B�e�ł��A���̊ԓV�C�̈���������̕����A�㔼�A�A�|�C�x�o�R��������D�V�ɓ]���A�O��̃q���`���}�_���Z�Z�����B�e�ł����ق��A�ŏI���ɂ͍X�ɋC�����オ��A����Ǝv���Ă����G�]�q���V���`���E�A�I�I�����V���`���E�����邱�Ƃ��ł��A�قږ��_�̐��ʂł������B�\�肪�t��������A����قǂ̐��ʂ͖��������Ǝv���A������ݒ肵��Mn����ƍK�^�Ɋ�������B�@�@�@�@�@�@�@ ���d�R�����I�s�i2019�j-�g�ƊԂ̋L��- �@�@�@�@�@�@�����̑��̍����̎ʐ^�͂�����@�@���@�@���d�R�����Ō������@�@�@�@���d�R�����Ō������̑��̍������@ |



 �@�@
�@�@ 











 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@



 �@�@
�@�@










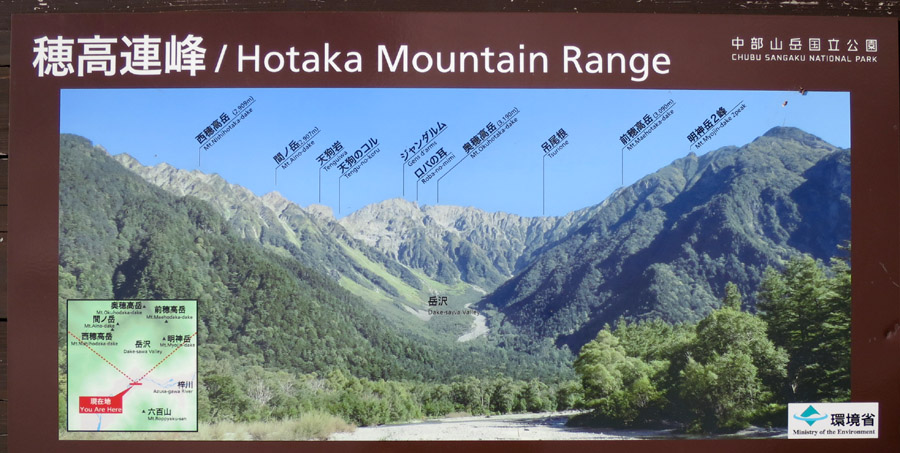








 �@
�@
 �@
�@

 �@
�@
 �@
�@

 �@
�@
 �@
�@
 �@
�@



 �@
�@
 �@
�@

 �@
�@